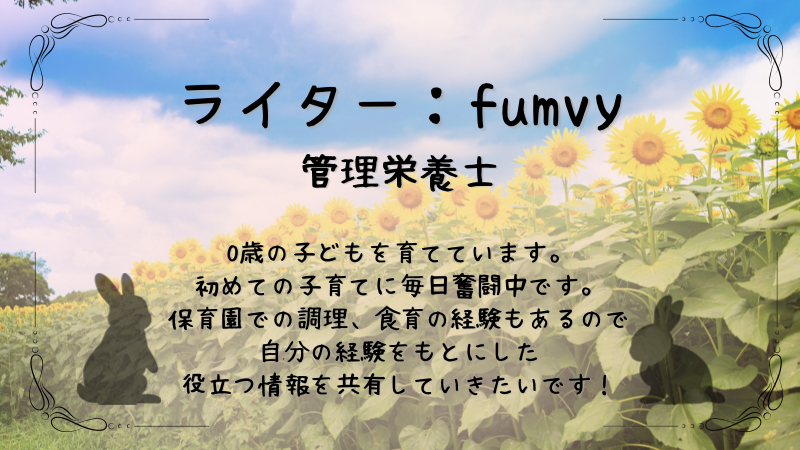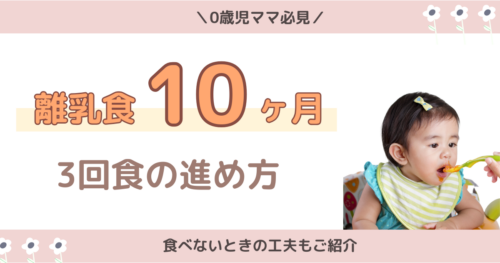手軽に食べられて甘くておいしいバナナは、子どもから大人まで親しみやすい食材です。
季節を問わず手に入りやすく下処理も簡単なのが嬉しいですよね。
この記事では、初めて赤ちゃんにバナナを与える際の以下の疑問について解説していきます。
・どんな準備をしたらいいのか
・どのように調理すればいいのか
・どのぐらいの量を与えたらいいのか
・初期〜完了期までどのように進めていけばいいのか
赤ちゃんの成長段階に合わせて、離乳食にバナナをぜひ取り入れてみてくださいね。
目次
バナナはいつから食べられる?

バナナは離乳食初期(生後5~6ヶ月)から食べることができて、手軽に与えられる食材です。
甘い味で子どもが好みやすく、とろみがあって食べやすいのが特徴です。
お粥や野菜に慣れてきたら取り入れてみましょう。
また、私の娘はバナナが大好きで、いつもデザートとして喜んでおいしそうに食べています。
1.月齢別の目安

バナナに限らず初めて食べる食材は加熱したものをスプーン1杯から始めることが大切です。
以下に離乳食初期〜完了期までの1回あたりの野菜・果物の月齢別の目安量を記載しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
※バナナ単体の量の目安は、後述の「離乳食初期のバナナの調理方法」「離乳食中期・後期・完了期のバナナ」に記載していますので是非そちらも参考になさってください。
- 初期(5~6ヶ月):なめらかにすりつぶして加熱したものをベビースプーン1杯〜10g
- 中期(7~8ヶ月):舌でつぶせる硬さで加熱したもの20~30g
- 後期(9~11ヶ月):歯茎でつぶせる硬さのもの30~40g
- 完了期(12〜18ヶ月):歯茎で噛める硬さのもの40〜50g
アレルギーなどが疑われる症状が万が一出た場合に、すぐ病院を受診できるように、食べさせるタイミングは平日の午前中を選びましょう。
2.バナナの栄養

バナナには赤ちゃんの成長や健康に欠かせない下記のような栄養素が含まれています。
・ビタミンB群(エネルギー、脂質、たんぱく質など体内での代謝に関わる)
・カリウム(細胞内の浸透圧や血圧の調節、筋肉や神経への伝達に関わる)
・食物繊維(便通や腸内環境を整える)
ただし、バナナには糖質も多く含まれているため、食べすぎには注意が必要です。
他の食材とのバランスを考えて与えましょう。
3.アレルギーに注意

バナナは「特定原材料等28品目」に指定されているアレルギー食材の一つです。
下記が主な症状です。
・皮膚のかゆみや赤み、蕁麻疹
・腹痛や下痢
・目のかゆみやくしゃみ
初めて与える際は必ず少量から始め、赤ちゃんの様子を慎重に観察します。
アレルゲンは加熱に弱いと言われていますが、加熱されていても症状が出ることもあるので注意が必要です。
万が一症状が出た場合には、速やかに病院を受診してください。
アレルギー症状が出た際の対応については、以下の記事も参考にしてみてくださいね。
離乳食初期のバナナの作り方

離乳食初期の場合は電子レンジ加熱で簡単に作ることができます。
特に初期はなめらかなペースト状にする必要があるので、ブレンダーやすり鉢などを準備すると簡単に時短で作ることが出来ますよ。
以下ではバナナの選び方や具体的な調理方法についても記載しますので是非参考になさってくださいね。
1.バナナの選び方

離乳食のバナナは、房の付け根が太くてしっかりしており、ずんぐりとした形のものがおすすめです。
さらに、皮の表面に黒い斑点(シュガースポット)が出ているものを選びましょう。
まだ青みがかっていて硬い場合は、暖かい部屋に置いたり、りんごと一緒に保管したりすると十分に熟して自然な甘みが増し、赤ちゃんが食べやすい状態になります。
テーブルなどに置いて接触している部分は傷みやすいので、スタンド等を利用して保管するのがおすすめです。
2.離乳食初期のバナナの調理方法

大人が普段食べている状態と異なるので、特に離乳食初期はどのように調理したらいいか悩みますよね。
手間がかかるイメージがあるかもしれませんが、意外と簡単です。
以下に、バナナの離乳食初期の材料や作り方について順に記載していきますね。
〈材料〉
・バナナ 1〜2cm分
・水 大さじ3
※最初はベビースプーン1杯程度から始め、徐々に量を増やしていく
〈作り方〉
①バナナの皮をむき5mmぐらいの厚さの輪切りにする
②耐熱容器に切ったバナナと水を入れる
③ふんわりとラップをかけて電子レンジ(600W)で約40秒加熱する
④すり鉢やブレンダーでなめらかになるまですりつぶす
なお、離乳食を始めたばかりの場合は、繊維の多い中心部(芯の茶色っぽい部分)は使わず、すりつぶした後に裏ごしすることをおすすめします。
粘度が高い場合には湯冷ましの水を少しずつ加えて調整してください。
バナナは空気に触れると黒く変色しますが、変色しても傷んでいるわけではないの安心してくださいね。
3.赤ちゃんもお手伝い!

密閉できる袋に軽く手でちぎったバナナを入れて赤ちゃんに渡して、”もみもみ”つぶしてもらいましょう。
私の娘はテーブルに置いて、”だんだん”手を振り下ろして叩きつぶして楽しんでいました。
お手伝いしてもらって親子で離乳食作りを楽しみましょう。
離乳食中期・後期・完了期のバナナ

離乳食中期から完了期にかけて、赤ちゃんの成長に合わせて変化させていきましょう。
1.ステップアップの仕方

月齢はあくまでも目安なので、赤ちゃんのペースに合わせて調整してくださいね。
初期(生後5~6ヶ月)
- 1食あたりの目安量:他の野菜と合わせて15~20g
- バナナ単体の量:少量(約1〜2cm)
- 形状:ペースト状
- 調理方法:なめらかになるまでつぶす
中期(生後7~8ヶ月)
- 1食あたりの目安量:他の野菜と合わせて20~30g
- バナナ単体の量:約10g(約2〜3cm)
- 形状:舌でつぶせる豆腐くらいの硬さ
- 調理方法:粗くつぶす
後期(生後9~11ヶ月)
- 1食あたりの目安量:他の野菜と合わせて30~40g
- バナナ単体の量:10~15g(約2〜3cm)
- 形状:歯茎でつぶせる硬さ、5~7mm角に切る
- 手づかみ食べの場合:縦に6つ割りにして4~5cmの長さのスティック状、もしくは約5mmに薄く輪切り
赤ちゃんの「自分で食べたい!」「触りたい!」という意欲が高まる後期では、手づかみ食べを積極的に取り入れましょう。
ただし、窒息の危険性もあるため、赤ちゃんの様子に合わせて加熱してやわらかくしたり、細さや薄さを調節してカットしたりしましょう。
完了期(生後12~18ヶ月)
- 1食あたりの目安量:他の野菜と合わせて40~50g
- バナナ単体の量:15~20g(約3〜4cm)
- 形状:歯茎で噛める硬さで、縦に4等分程度に切る
きなこやヨーグルトに混ぜたり、蒸しパンに入れたり、いろいろなアレンジができるのでバナナはおやつにもピッタリですね。
BLW離乳食や手づかみ食べについての以下の記事もぜひ参考にしてみてください。
2.いつから生で食べられる?

加熱せずに生で食べられるようになると調理の手間が減って、お出かけにも手軽に持っていくことができて便利ですよね。
ただ、食中毒等の衛生面やアレルギーの観点からは、少なくとも中期までは加熱をした方が安心できると思います。
加熱することで柔らかくなって食べやすくなるので、後期以降も赤ちゃんの様子次第で必要に応じて加熱して与えましょう。
もしよければ以下の記事も参考にしてみてくださいね。
↓↓↓
一般社団法人母子栄養協会:「バナナはいつまで加熱する?離乳食での使い方」
作り置きで時短!

冷凍保存することで少しでも楽をしましょう。
小分けに冷凍できるトレーが便利です。容量サイズもいくつか種類があるので食材や時期に合わせて使い分けることができます。
冷凍庫のスペースが狭くて保管場所に悩む場合は、密閉できる袋に平らにして入れて、箸などを使ってブロック分けをして冷凍するといいかもしれません。
1.保存方法

以下、大切なポイントです。
・清潔な袋や容器(トレー)に入れて冷凍する
・冷凍した日付と使用期限(1週間後)を記入する
・食べ残しは冷凍せず、当日中に使い切る
2.解凍方法

解凍方法について以下に記載します。
・必ず加熱して解凍する(自然解凍は避ける)
・1食分を耐熱皿に移し、ラップをかけて加熱する
・ 電子レンジ(600W)での加熱時間の目安
初期:約20秒
中期:約40秒
後期:約1分
加熱後は必ず粗熱を取ってから与えましょう。
水分が飛びすぎた場合は、少量の水を加えて加熱すると適度な硬さに調整できます。
まとめ

離乳食でのバナナの活用は、忙しいママでも手軽に簡単に作れて便利なためおすすめの食材のひとつでもあります。
赤ちゃんの成長に合わせて形状や量を調整し、様子を見ながら進めることで、安全で栄養価の高い離乳食としてバナナを取り入れることができます。
なお、バナナを使用する際には赤ちゃんの成長段階に合わせた調整が大切で、バナナには豊富な栄養素が含まれる一方で、アレルギーの可能性もあるため、最初に取り入れる時には様子を見ながら注意して与える必要もあります。
「なかなか食べられるようにならない」「少しの量しか食べられない」など悩んでいる方も多いと思いますが、離乳食の食べ進みや赤ちゃんの好き嫌いには個人差がありますので、焦らず赤ちゃんのペースで進めていけば大丈夫。
作り置きやベビーフードなどをうまく活用しながら、親子で楽しい食事の時間を作っていきましょう!