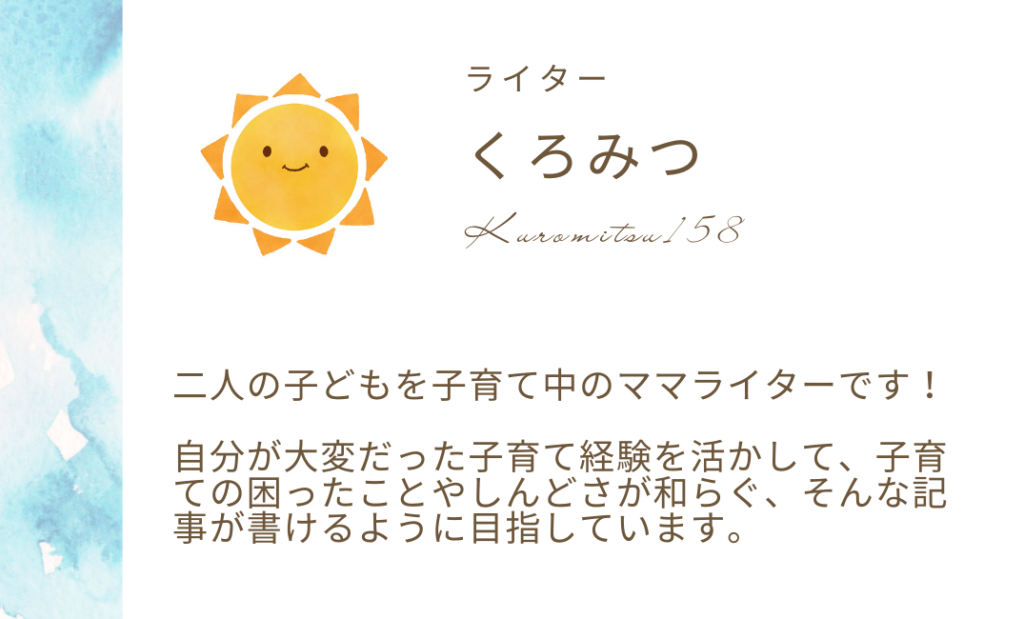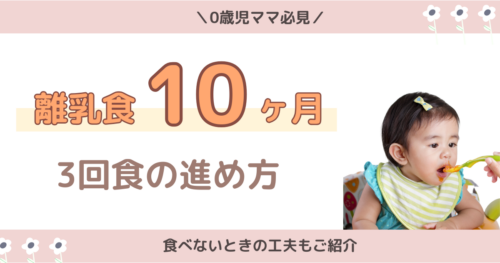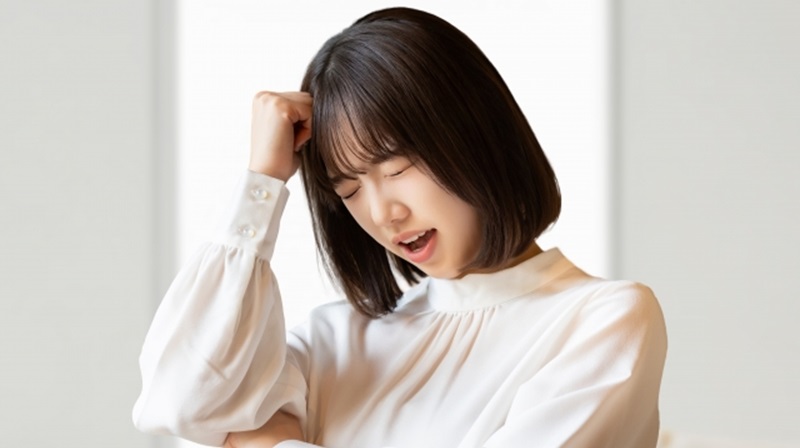
保育園でも毎日のように使うお食事エプロン。
でも「気づいたらカビが…」そんな経験ありませんか?
毎日忙しいママだからこそ、カビ対策を3ステップで簡単に済ませましょう!
目次
1.お食事エプロンにカビが生えるのはなぜ?

その原因を詳しく解説していきます。
①湿気が残る環境

湿気はカビにとって「生きるための水分」なので、湿った環境が続くとすぐに増殖してしまいます。
カビは高温多湿の環境を好み、湿度が60%を超えると活発になります。
湿度80%以上の環境ではわずか1日で繁殖することも!
エプロンが湿った状態で長時間放置されると、表面にカビの胞子が定着しやすくなります。
②食べ物や飲み物の汚れが残る

子どもが使うエプロンは食べこぼしが多く、これがカビにとってのエサになってしまいます。
特にごはん粒やパンくずのような炭水化物、ミルクやヨーグルトのような乳製品、ジュースのような糖分はカビにとってはごちそうです。
これらの食べこぼしがエプロンに付着したままになると、カビにとって繁殖しやすい環境になってしまい、短時間で菌が増殖します。
③通気性の悪い保管場所が原因

カビは湿度60%以上になると活発になるため、湿度の高い場所に置いたままにしないようにしましょう。
例えば、保育園から持ち帰るためのビニール袋に入れっぱなしにしたり、洗濯機に入れたまま置いておいたりすると、カビの増殖を加速させてしまいます。
保育園から持ち帰ったらなるべくお手入れをしてあげましょう。
また、エプロンを洗濯後乾ききらないままクローゼットなどで保管することも、カビの繁殖の原因になります。
2.保育園で使った後にすぐできるカビ対策3選

ここからは、保育園での使い方から帰宅後のお手入れまで、具体的な方法をご紹介します!
①保育園から持ち帰る時の工夫(防水/メッシュ)
保育園で使ったお食事エプロンを、どうやって持ち帰るかもカビないようにする上で大切なポイントです。
防水バッグやビニールを使う

水分や汚れを通さないため、ほかの荷物に汚れなどがつくのを防いでくれます。
ただし、密閉されている分、湿気がこもりやすいので家に帰ったらすぐに取り出しましょう。 メッシュバッグを使う

引用:ダイソーネットストアお食事エプロンの持ち帰りには、通気性のよいメッシュバッグも便利です。
カビは湿度の高いところで発生しやすいので、空気の通りが良いメッシュバッグはカビ予防に効果的です。
メッシュバッグは100円ショップなどで購入できます。
②カビにくい素材を選ぶ(シリコン・撥水ナイロンなど)

以下に素材別の特徴をまとめましたので、参考にしてみてください。
| 素材 | 良い点 | 悪い点 | カビやすさ |
|---|---|---|---|
| シリコン・プラ製 | 防水性が高く乾きが早い | 重量が重くなりやすく首や肩に負担がかかる | カビにくい |
| ナイロン製 | 軽くて柔らかく撥水性があり乾きも早い 洗濯機で洗える | 洗濯により撥水効果が薄れてくると水を弾きにくくなる | カビにくい |
| 布製 | 軽くて柔らかくつけ心地◎ 洗濯機で洗える | 乾きにくく汚れが落ちにくい シミがつきやすい | カビやすい |
布製の場合は、乾きやすいタイプを選ぶと良いでしょう。
シリコン製・プラスチック製のお食事エプロンは、保育園によっては使用不可の場合もあるため、事前に確認するのがおすすめです。
③帰宅後すぐのお手入れ(軽く水洗い・つけ置き・しっかり乾燥)

少しの手間でカビを防ぐことができますので、ぜひ試してみてください。 軽く水洗いする

簡単な水洗いでも、エプロンに残った食べ物のカスや飲み物の成分を落とすことでカビ予防の大きな効果があります。
冷たい水を使うよりも、ぬるま湯のほうが汚れが落ちやすくおすすめです。
特に、食べ物がたまりやすい縫い目部分やポケットの部分を念入りに洗いましょう。
水洗いの後はなるべく早く洗濯機で洗いましょう。 必要に応じてつけ置き洗いを

ただし、素材によってはダメージを与える場合もあるため、注意して使いましょう。
おすすめは「Rinenna(リネンナ)」というつけ置き洗い用洗剤です。
桶やバケツにリネンナを入れてぬるま湯を流し入れます。
泡だったところにお食事エプロンを入れて数時間つけ置き、つけ置きの液ごと洗濯機に入れて洗うだけ!
カビ汚れだけでなく、シミや臭いもすっきり落ちる優れものです。
↓↓↓【リネンナ】のおためしはこちらから ↓↓↓
着色よごれに!つけおきメイン洗濯洗剤[おためし] しっかり乾燥させる

湿り気が残ったまま保管すると、カビの原因になってしまいます。
布製エプロンの場合、洗濯機で脱水してから風通しの良い場所に干します。
ハンガーや洗濯ばさみを使って広げて干すと乾きが早く、カビの予防につながります。
シリコンやプラスチック製のエプロンの場合は、タオルなどでしっかり水気を拭き取った後、完全に水分が飛ぶまで干しておきましょう。
梅雨時などの湿気が多い季節には、サーキュレーターや扇風機などの風を当てると乾きが早くなります。
乾燥させた後は湿気の少ない場所に保管しましょう。
3.それでもカビが出てしまった時の対処法

ここからは、お食事エプロンがカビてしまった時の対処法についてご紹介していきます。
①酸素系漂白剤でつけ置き洗い

酵素系漂白剤(オキシクリーン、ワイドハイターなど)を使ってつけ置き洗いをします。
漂白剤をぬるま湯に溶かし、エプロンをつけ置きします。
つけ置き時間は漂白剤の製品説明書に従ってください。
つけている間に、ブラシでカビの部分を軽くこすると効果的です。
つけ置きが終わったら丁寧にすすぎ、漂白剤が完全に落ちるようにしてください。
特に赤ちゃんや子どもが使うアイテムなので、洗剤が残らないよう念入りにすすぎましょう。
ただし、漂白剤の使用は、メーカーによっては使用NGの場合もありますので、洗濯表示をしっかりと確認してください。
もし使用される場合は、各自の判断でご使用をおねがいします。
②お酢を使ったナチュラルクリーニング

赤ちゃんが使う物に漂白剤は使いたくない…という方には「お酢」がおすすめです。
お酢には殺菌効果があり、カビの殺菌にも効果があります。
水1Lに対し、酢(穀物酢)を大さじ1~2加え、30分程度つけ置きします。
その後、通常通り洗濯すればOK。
注意点は、砂糖の入っていないお酢を使用することです。リンゴ酢や黒酢などは砂糖が入っているため避けましょう。
殺菌効果があるだけでなく、洗濯物をふんわりと肌触り良く仕上げてくれます。
③頑固なカビには重曹+漂白剤で丁寧ケア

頑固なポツポツ黒カビには、重曹と漂白剤のペーストもおすすめ。
重曹に少量の塩素系漂白剤を加え、ペースト状にします。
カビの部分に塗り、ラップをして一日程度置いてからブラシで優しくこすります。
その後、よく水で洗い流し、通常通り洗濯してください。
この方法は、頑固な黒カビにもきれいに落ちると評判の方法ですが、色落ちしてしまう原因につながるため色柄物には向きません。
また、塩素系漂白剤は酸性のものと混ぜるととても危険です。
もし使用される場合は、各自の判断で十分に注意してご使用をおねがいします。
カビが生えてしまったときの対策や予防法は、以下の記事でも解説していますので参考にしてみてくださいね。
4.まとめ|毎日を清潔&快適にするために

少しの手間で、エプロンを長く使えてママの負担も軽くなります。
保育園生活で使うアイテムだからこそ、きちんと守っていきましょう!