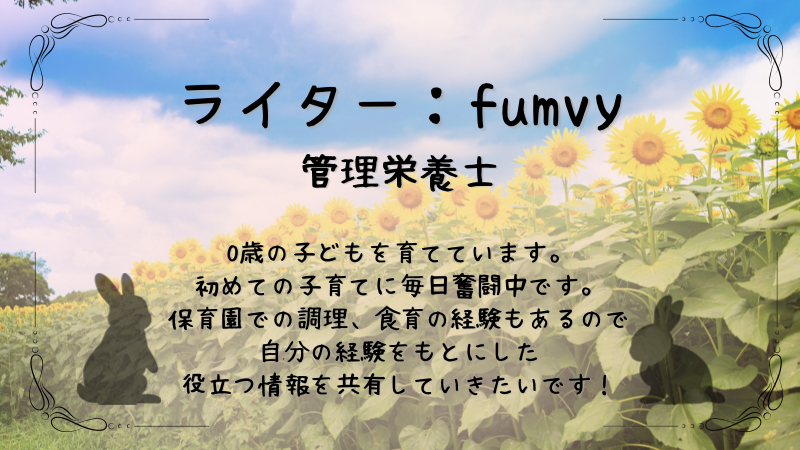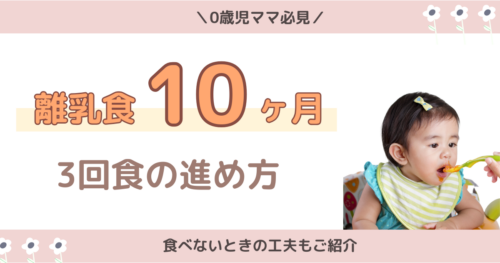離乳食をスタートしてお粥や野菜に慣れてきたら、次のステップとしてたんぱく質を多く含む食材に挑戦しましょう。
豆腐は離乳食初期の初めてのたんぱく質として最適な食材です。
柔らかくて歯がまだ生えそろっていない赤ちゃんにも食べやすく、調理の手間も少ないのでおすすめです。
この記事では、豆腐の離乳食の調理方法、月齢別の分量と形態、初期〜完了期までの進め方と豆腐の活用例、豆腐の冷凍保存などについて解説していきます。
なお、豆腐はたんぱく質以外にもカルシウムや鉄分などの栄養もたくさん含まれているので、手軽に食べられる豆腐をうまく活用しながら、離乳食を進めていきましょう。
目次
豆腐はいつから試す?

豆腐は離乳食初期(生後5~6ヶ月)から食べることができますが、まずはお粥と野菜に慣れるのが先です。
だいたい離乳食を始めてから2〜3週目ぐらいから試すのがいいと思います。
ただし、豆腐には大豆が含まれるのでアレルギー症状が出る可能性もあります。
初めて食べる際は、すぐに病院を受診できる時間帯にスプーン1杯から始めましょう。
豆腐が問題なく食べられても、他の大豆製品(納豆や豆乳など)ではアレルギー症状が出ないとは限らないので油断しないようにしてくださいね。
※万が一、アレルギーが疑われる場合には速やかに病院を受診してください。
豆腐の栄養

豆腐の原料である大豆は「畑の肉」と呼ばれるぐらい、植物性たんぱく質が豊富に含まれています。
下記のように赤ちゃんの成長に大切な栄養素を含む優秀な食材です。
・たんぱく質(筋肉や臓器など体の組織を作る)
・鉄分(赤血球に含まれるヘモグロビンの主成分、酸素を体内で運ぶ)
・カルシウム(歯や骨を作る、筋肉の収縮や神経伝達に関わる)
生まれてくる前に体内に貯蔵していた鉄分が、だいたい生後6ヶ月ごろになくなると言われています。
母乳に含まれる鉄分の量は多くないため、特に母乳育児の場合には、離乳食で鉄分を補うことが大切です。
下記の食材にも鉄分が多く含まれています。
・レバー
・カツオ
・マグロ
・大豆製品(納豆、厚揚げなど)
・小松菜
・ほうれん草
特に大豆製品は、調理の手間が少ないものが多いので、離乳食にも取り入れやすいですよね。
また、粉ミルクを離乳食に取り入れるのもおすすめですよ。
赤ちゃんの離乳食開始後の栄養バランスについて、以下の記事もぜひ参考にしてください。
↓↓↓
離乳食の豆腐の選び方

豆腐にもいろいろな種類があるので、赤ちゃんの成長や好みなどに合わせて選びましょう。
・絹豆腐(やわらかくて舌触りもなめらかなので初期にもおすすめ)
・木綿豆腐(鉄分は多く含まれるが食感が硬いので、ある程度噛んで食べられるようになってからがおすすめ)
・充填豆腐(賞味期限が長くて使いやすく、絹豆腐と同じようなやわらかさで初期にもおすすめ)
充填豆腐の中には35gや50gずつの小分けパックの商品も販売されています。
私は、無駄が少なくて使いやすい小分けパックを最大限に活用しています。
私が活用している豆腐はこちら↓↓
ぜひ参考にしてみてくださいね。
1.豆腐は加熱すべきか

豆腐は加熱しなくても食べられますが、免疫が不十分な赤ちゃんのためには1歳ぐらいまでは加熱して食べさせるようにしましょう。
沸騰したお湯でゆでる方法もありますが、洗い物も少なく手軽なので、私は電子レンジ加熱をおすすめします。
加熱しすぎると硬くなって赤ちゃんが食べづらくなってしまうので、様子を見ながら加熱するようにしてくださいね。
また、豆腐は賞味期限が短い食材なので注意しましょう。
適切な温度で冷蔵保存を行うことも大切です。
2.高野豆腐も離乳食に使える?

豆腐の仲間の「高野豆腐」も実は離乳食に使えます。
すりおろせば初期から使えますし、後期以降は水で戻して小さく切れば食べられます。
豆腐を凍らせて乾燥させたものなので、常温で保存ができるのが嬉しいですよね。
(豆腐や肉魚を買い忘れた時に、高野豆腐に何度助けられたことか・・・)
小さくカットされている商品もあって便利なので、豆腐に食べ慣れてきたらぜひ試してみてください。
離乳食初期の豆腐の作り方

加熱に時間がかかる野菜などに比べると、つぶすのも簡単で短時間で作ることができます。
以下に、材料や作り方について順に記載していきますね。
〈材料〉
・絹豆腐 15g
・水 大さじ1
〈作り方〉
①耐熱皿に豆腐と水を入れてラップをかける。
②電子レンジ(600w)で約20秒加熱する。
※必要に応じて加熱時間を調節してください。加熱後は火傷にご注意ください。
③ブレンダーやすり鉢ですりつぶす。
赤ちゃんにお手伝いをお願いしよう!

豆腐をつぶすお手伝いを赤ちゃんにお願いしてみましょう。
五感を刺激して赤ちゃんの発達を促す「感覚遊び」として食材を活用することもできます。
ジップロックの中に豆腐を入れてつぶしてもらえば、掃除の手間もいらないのでおすすめです。
「感覚遊び」に振り切る場合は、絹豆腐、木綿豆腐、高野豆腐を触って比較すると楽しいかもしれませんね。
離乳食中期・後期・完了期の豆腐

野菜・果物と異なり、たんぱく質は食材によって1食あたりの目安量が違うので注意してください。
肉や魚に比べると、豆腐は目安量が多いです。
どのように豆腐の分量や形状を変化させていくべきか、以下に記載していきますね。
1.月齢別の目安とステップアップの仕方

豆腐は元々やわらかいですが、大きすぎる切り方で食べさせることは誤嚥のリスクもあるのでやめましょう。
赤ちゃんの様子を観察しながら、少しずつステップアップさせてください。
※月齢はあくまでも目安なので、赤ちゃんのペースに合わせて調整してくださいね。
初期(生後5~6ヶ月)
- 1食あたりの目安量:15~20g
- 形状:なめらかなペースト状
- 調理方法:加熱して粗くつぶす
中期(生後7~8ヶ月)
- 1食あたりの目安量:30~40g
- 形状:舌でつぶせる硬さ
- 調理方法:加熱して4〜5mm角に切る
後期(生後9~11ヶ月)
- 1食あたりの目安量:45g
- 形状:歯茎でつぶせる硬さ
- 調理方法:加熱して5mm〜1cm角に切る
完了期(生後12~18ヶ月)
- 1食あたりの目安量:50~55g
- 形状:歯茎で噛める硬さ
- 調理方法:1cm〜一口大に切る(大人と同じ大きさで大丈夫になってきます)
2.豆腐の活用例について

豆腐は淡白な味なので、豆腐単体でたくさん食べるのは飽きてしまう赤ちゃんもいるかもしれません。
いろいろな料理に入れてアレンジしてみましょう。
いくつか活用例を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
豆腐の水切りは、ペーパーで豆腐を包んで電子レンジ(600w)で2〜3分加熱すると簡単ですよ。
※豆腐(300g)1丁の場合
・野菜のおやき
ほうれん草やかぼちゃなどを入れたおやきは、手づかみ食べにもおすすめです。
豆腐と野菜を混ぜて、少量の片栗粉で硬さを調節して焼くだけで簡単なのでぜひ作ってみてください。
私は一週間分を一度に作って焼いたものを冷凍保存しています。
・豆腐のハンバーグ
ひき肉だけだと赤ちゃんには硬くて食べづらいことも多いです。
豆腐を混ぜることでふわふわでやわらかくなって食べやすくなりますよ。
焼いたものを冷凍保存もできますが、大人のハンバーグを作るときに取り分けるのもおすすめです。
・野菜の白和え
野菜につぶした豆腐を混ぜるだけで、簡単にたんぱく質も合わせて補給できるメニューになります。
ぜひにんじんやほうれん草などと合わせてみてください。
野菜から水分も出るので冷凍保存には向かないので、1回分を作るか、大人の分から取り分けましょう。
豆腐の冷凍保存について

作り置きすることで手間を省けるので、基本的には離乳食の冷凍保存をおすすめしたいのですが・・・・
私は豆腐は冷凍に向かない食材だと思っています。
加熱してつぶしたものを冷凍してみたところ、ボロボロになり私の娘はあまり食べてくれませんでした。
解凍後にもう一度すりつぶして試してもダメでした・・・
離乳食において、食材の大きさや硬さだけでなく”食感”も大切ですよね。
300gや200g×2Pなどの規格だと作り置きじゃない場合、大人の料理に使わないとほとんどがロスになります。
(開封後はできるだけすぐに使い切るのが望ましいので、離乳食だけだと使いきれません)
私は無駄にならないような大人の料理と離乳食の組み合わせを考える余裕がなかったので、先ほど紹介した「豆皿豆腐(35g×8P)」を使っていました。
初めて商品を見つけた時、「これは離乳食のための豆腐では!?」と感動しました。
パックを開けて皿に移してレンジで加熱するだけで済むので、作り置きしなくても負担がなくてとても楽なので心からおすすめしたいです。
余談(ライターの経験談)

もりもり食べる食材もあれば、なかなか食べてくれない食材もありますよね?
娘に初めて”すいか”をあげてみた時、味と食感が苦手なのかほとんど食べてくれませんでした。
細かく刻んでみたり、よく加熱してみたり、いろいろ工夫しましたがお気に召さず。
もしかして苦手なのかなと思いつつ、2週間後にもう一度あげてみたところ・・・・
口いっぱいに頬張っておいしそうに爆食いしてびっくりでした。笑
今ではすいかが大好物です。
いきなり食べられるようになることもありますし、食べないことに悩み過ぎずに赤ちゃんのペースで進めていきましょう!
まとめ

豆腐は、お粥や野菜に慣れてきてからのたんぱく質を試す食材として最適です。
野菜のように下処理の手間がないのも忙しいママに嬉しいポイントですね。
冷凍に向かない食材だと思いますが、便利な商品を活用すれば取り入れやすいです。
母乳やミルクで栄養をとっていた赤ちゃんが、少しずつ食材から栄養をとる練習をしていく過程はとても尊いですよね。
でも練習に付き合うママもパパもなかなか大変・・・
せっかく手間をかけて作った離乳食を食べてくれないのは悲しいですよね。
いきなり食べるようになったり、逆に食べなくなったり、赤ちゃんの気分次第なこともあるかもしれません。
離乳食は大変なことも多いですが、練習に励む赤ちゃんの成長を楽しみながら見守っていきましょうね!