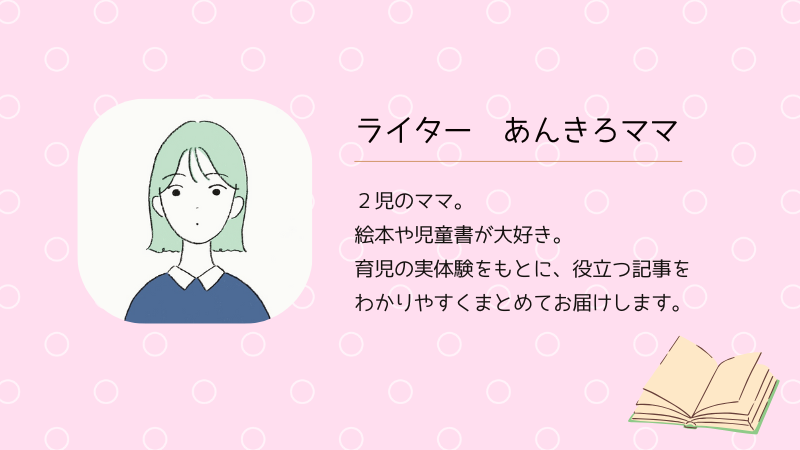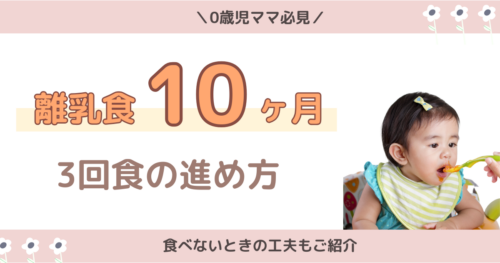「せっかく作ったのに食べてくれない」
「好きなものしか口にしない」
そんな悩みを持っているママはきっと多いはず。
離乳食を卒業し、幼児食へと移る1~3歳の時期は、とくに好き嫌いや偏食が激しい時期。
せっかく幼児食に進んだから食事でしっかり栄養を取らせたくて頑張って作っても、バランス良く食べてもらえないと、ママはついイライラしてしまいますよね。
楽しいはずの食卓が、親子でプレッシャーになってしまうことも。
でも、大丈夫です。
幼児食の「食べない」悩みは、誰にでもやってくるもの。
この記事では、私が幼児食の悩みを乗り越えた9つの工夫についてご紹介します。
完璧を目指すのではなく、親子で食を楽しむ時間を作っていきましょう。
目次
「食べない日があっても大丈夫」と考える

昨日はおかわりしたのに、今日はほとんど食べてくれない・・・なんてことが、幼児食の頃はしょっちゅう起こります。
それは、ママやパパの料理が悪いからではありません。
1~3歳の子は体が小さく、胃もまだ成長途中。
気温や睡眠、体調、運動量によっても、食べられる量が違います。
大切なのは「毎食バランス良く食べさせる」のではなく、「数日単位でバランスを取れたらいい」という気持ちを持つことです。
今日の夕食で肉や魚を食べなくても、翌朝に卵や乳製品を食べられたなら、それで十分。
3日くらいのスパンで栄養バランスを見ると、心がずっとラクになりますよ。 完食よりも「食べることが楽しい」を優先する

つい全部食べてほしいと思ってしまいますが、まずは「食べることが楽しい」という気持ちを育てることを優先しましょう。
「おいしいね」「これ好きだよね」といった前向きな言葉をかけてあげることで、食卓が楽しい雰囲気になります。
逆に、「残さず食べて」「一口でも食べて」とプレッシャーをかけると、子どもはますます食べたがらなくなることも。
残さず食べる練習は、もう少し大きくなってから始めても間に合います。
1~3歳の幼児食は、食べることへの好奇心を育てることを大切にしてあげてください。
まずは、完食より「食べることが好き」を目標にしてみましょう。
親がモリモリ食べる

忙しい夕食時などには、子どもだけ先に食事をさせる場合があると思いますが、できるだけママやパパと一緒に食事をするのがおすすめです。
また、親子で同じメニューを食べると、子どもの興味を引きやすいです。
私は、幼児食の頃は子どもと向き合って食事を取り、親がモリモリ食べる様子を見せることを意識していました。
「おいしい~」と大げさな演技をする必要はありません。
普通に、自分が食べたいものをおいしく味わう様子を見せるだけでいいです。
お子さんよりもまずは、ママやパパが食事を楽しんでくださいね。
食べないときは無理に食べさせない

どんなに一生懸命作っても、おいしそうなレシピ通りに作っても、子どもが嫌がる日があります。
そんなとき、「一口だけでも食べて」「これだけでいいから」と言いたくなりますが、無理に食べさせようとすると、子どもはかえって嫌がることも。
ママがイライラして食卓の雰囲気がピリピリすると、食事のイメージが悪くなってしまいます。
イライラはぐっとこらえて、「また明日食べようか」と軽く流せるように頑張りましょう。
まったく食べなかったメニューも、次に出したら意外と食べてくれることがあります。
その逆に、大好きだと思って作ったら、まったく食べてくれない日もあります。
幼児食の頃はとくに、子どもの食欲は気まぐれなので、焦らずに見守りましょう。

見慣れない料理を前にすると、子どもは警戒します。
初めに警戒されると食べさせるのが難しくなるので、子どもが安心して食べられるメニューを意識しましょう。
好きな味の中に新しい食材を混ぜてあげると、すんなり受け入れてくれることがあります。
たとえば、子どもが好きなパンケーキにすりおろした野菜を加えたり、カレーに新しい具材を入れたりして、工夫してみましょう。
また、子どもは食べ慣れた味が安心するので、好きな食べ方があれば、無理にいろいろな調理法を試さなくても大丈夫です。
我が家では、ブロッコリーはゆでる、ピーマンはだし煮、にんじんはグラッセがお決まりでした。
それ以外の調理法ではあまり食べてくれませんでしたが、最近では様々な料理も食べるようになりましたよ。
食べやすい固さに調節する

味は好みだけど、固さがネックで食べてくれないことがあります。
繊維質の多い野菜やお肉は、子どもにとって噛みにくいので嫌がる子もいます。
うちの娘は、お肉や大根、りんごが「硬い」と言って4歳くらいまで食べませんでした。
今思うと、顎や歯が比較的細い子だったので、噛むのが大変だったのだと思います。
お肉がホロホロになるまで煮込んだり、りんごは煮りんごにしたりして工夫すると食べてくれることもありました。
でも、他に食べられるものがあるなら、無理に頑張らなくても大丈夫です。
我が家の場合、娘は4歳過ぎから噛む力が強くなり、別人のようにお肉が大好きになりましたよ。
今では煮りんごより硬くてシャキシャキしたりんごのほうが好きです。
顎の強さや成長には個人差があるので、お子さんの好みに合わせてあげてください。
お手伝いで食への興味をアップさせる

我が家は食育とお楽しみのために、よく野菜の収穫体験に行きました。
自分で収穫したピーマンやにんじんは、やっぱり食いつきがよくて、よく食べてくれましたよ。
野菜のお土産をたくさんもらえるので、大人も楽しくておすすめです。
お庭がある方は、家庭菜園で野菜を作るのもいいですね。
また、「おにぎりパーティ」や「納豆巻きパーティ」もよくしました。
ごはんとのりと具を用意したら、あとは自由に作ってもらいます。
手やテーブルは汚れますが、そこは我慢。
自分で作ると楽しいので、食欲もアップしてくれるはずです。
食べる環境を楽しくする

お気に入りのスプーンやキャラクターのお皿を使うだけで、子どもはうれしくなります。
食べ終わると底に絵柄が見えてくるお皿は、きれいに食べる意欲を後押ししてくれますよ。
かわいい紙皿やペーパーナプキンを使ってパーティ気分にしたり、床にレジャーシートをしいてピクニックスタイルにしたりすると、楽しい気持ちで食べられるかもしれません。
また、食事用の椅子にシールを貼ったり、きれいなランチョンマットを使用してみたりして、お子さんが食卓を好きになるように工夫してみてくださいね。
親がラクする日を作ってOK

毎日手作りの食事を用意するのは疲れてしまいますよね。
そんなときは、積極的に手を抜く日を作るのがおすすめです。
我が家では、もっぱら金曜日の夜は手抜きDAYでした。
大好きなアンパンマンカレーやベビーフードをあげたり、お味噌汁だけ作って各自でおにぎりを作ってもらったり、パンと目玉焼きという朝ごはんメニューを出したり・・・。
親は手抜きのつもりでも、なぜか我が家の子どもたちは大喜び。
忙しい日や疲れた日は、簡単で無理しないごはんで十分です。
完璧で栄養バランスの取れた食事を毎日目指すよりも、「おいしいね」と笑い合える食卓がいちばん大切なのではないでしょうか。
ママやパパが無理をしないことが、結果的に子どもの笑顔につながりますよ。
まとめ|幼児食は完璧じゃなくていい!

幼児食はまだまだ成長過程。完璧を目指す必要はありません。
「いずれ食べるようになる」「大きくなっているから大丈夫」と信じて、焦らず見守りましょう。
親子で向き合って食卓を囲み、「おいしいね」と笑い合える時間を増やしていけるといいですね。
頑張って作った料理を食べてもらえないと、落ち込みますよね。
それは、真剣に子どもと向き合っている証拠。
焦らず、比べず、笑顔で、難しい幼児食の時期を乗り越えましょう!