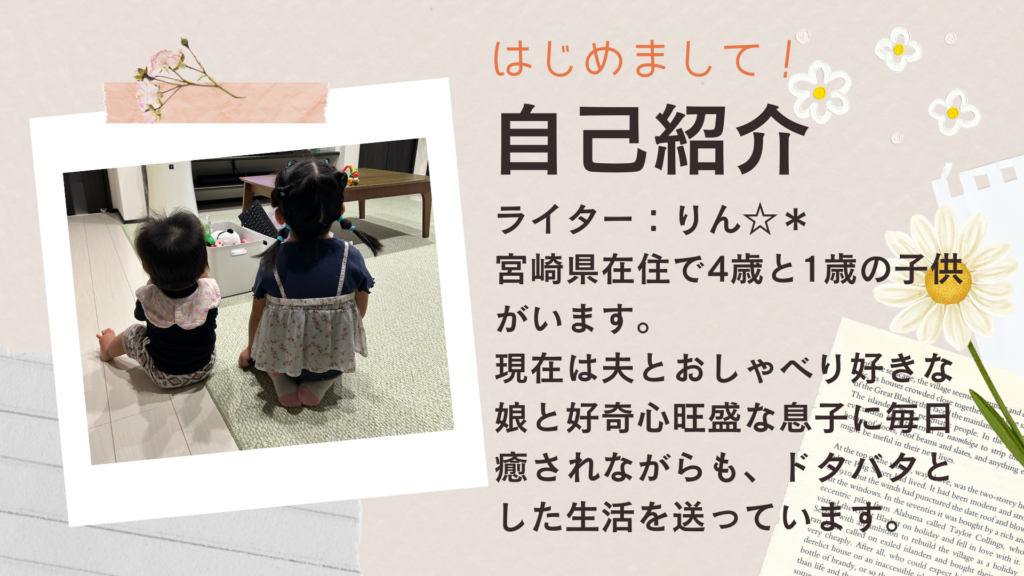仕事と子育てに追われる毎日、もうヘトヘト。そんなママ・パパも多いのではないでしょうか。特にお風呂タイムはワンオペ育児の最大の難関…。
子どもを安全に見ながら自分の身支度も済ませる必要があり、本当に気が抜けませんよね。そんなあなたに試してほしい5つの工夫をお伝えします。ちょっとした工夫でグッとお風呂じかんがラクになりますよ。
この記事では、忙しいママが今日から実践できる「お風呂じかんがラクになる5つの工夫」を紹介します。
目次
ワンオペ育児がつらい理由とよくある悩み

ワンオペ育児という言葉が当たり前のように使われるようになった今、多くの親がその過酷さに直面しているのではないでしょうか。
とくに共働きの家庭や、パートナーの帰宅が遅い家庭では、平日の育児や家事を1人でこなすことが当たり前のように求められており、心身ともに疲れ果ててしまうことも少なくありません。
仕事を終えて急いで保育園に迎えに行き、夕食を作り、子どもをお風呂に入れ、寝かしつける。自分のことはすべて後回しにして、子どものペースに合わせて生活する日々は、まさに時間との戦いですよね。
そしてその中で最も大変と感じる場面のひとつが、「お風呂タイム」ではないでしょうか。
心身ともに追い詰められる理由

ワンオペ育児でとくにつらいのは、物理的な疲れ以上に、孤独感やプレッシャーではないでしょうか。
誰にも頼れず、誰にも見られずにすべてのタスクをこなすことは、「ちゃんとやらなきゃ」「私がやらないと」という責任感を強くしてしまい、結果として自分を追い詰めてしまいます。
周囲の人に相談したり、少し頼ったりしたいと思っても、「迷惑になるかもしれない」「こんなことで弱音を吐いてはいけない」と思い込んでしまい、ますます孤独に感じてしまいますよね。
小さなストレスが積もっていくことで、些細なことで涙が出たり、イライラが止まらなくなったりするのも、決して珍しいことではありません。
お風呂タイムがワンオペの壁になる理由

日々の育児の中でも、お風呂の時間は1日で1位・2位を争うぐらい大変なシーンです。
赤ちゃんや小さい子供がいる家庭だと目が離せず、泣いたり動き回ったりするなかで、限られた時間で体を洗い、湯船に入れ、自分もさっと洗わなければなりません。
上の子がいれば、その子の安全確認や声かけも必要です。着替え、保湿、髪を乾かすなど、風呂上がりのケアも含めるとその負担は相当なものですよね。
さらに、浴室という閉鎖空間の中で、転倒や溺水のリスクにも常に注意を払わなくてはならないため、神経は張りつめたままになってしまいます。
また、自分が湯船に浸かってリラックスする余裕もなく、たった20〜30分のことのようでいて、精神的には1時間くらい長く感じらる時も…。
そうした状況が毎日続くと、ワンオペ育児のストレスは確実に積み重なっていきます。
けれども、ちょっとした工夫を取り入れることで、この大きなハードルを少しずつ乗り越えていくことができますよ。
ワンオペ育児をラクにする5つの工夫

ワンオペでの育児がつらいと感じるのは、ごく自然なことです。特にお風呂タイムは、体力も気力もぐったりしてしまう瞬間。
でも、ちょっとした工夫でぐんと楽になるんです。無理せず、自分にも優しくできるお風呂タイムにしていきましょう。
ここでは、仕事と育児の両立に悩むママ・パパに向けて、実際に取り入れやすい5つの具体的な方法を紹介します。
今日からすぐに試せる工夫ばかりなので、ぜひ気軽に取り入れてみてください。
工夫①:お風呂前の準備でスムーズに

お風呂の時間を少しでも快適にするには、入る前の「準備」が何より大切です。
お風呂に入りながら必要なものを取りに行くのは大変ですし、子どもから目を離すことにもなりかねません。あらかじめ流れを想定して段取りを組んでおくと、焦らずスムーズに行動できますよ。
お風呂に入る前に、まずはバスタオル、子どもの着替え、自分の着替え、おむつ、保湿クリームなどを脱衣所に準備しておきましょう。必要なアイテムをカゴやボックスにひとまとめにしておいたり、すぐに着れるように置いておくと、毎回の準備が楽になります。
加えて、子どもが湯冷めしないよう、部屋をあたためておいたり、温かい飲み物を用意しておくのも効果的。
事前に「お風呂セット」が揃っている状態にしておくだけで、ワンオペでも気持ちに余裕が生まれます。段取りが整っていると、お風呂上がりの慌ただしさも和らぎます。
工夫②:子どもの“待機時間”を乗り切るアイデア

ワンオペのお風呂で困るのが、自分を洗っている間など、子どもを少しだけ待たせる時間です。
ほんの数分でも目が離せない年齢の場合、どうやってその時間を安全に過ごさせるかが悩みどころになりますよね。
赤ちゃんの場合は、浴室用のベビーチェアを活用するのがおすすめです。自分の体を洗っている間も視界に入れておけるので安心感がありますよ。
少し大きくなった子どもには、防水のおもちゃや、スマホを防水ケースに入れてお気に入りの動画を見せるなど、時間をつなぐ方法もあります。
たとえば「これを見てる間にママはチャチャッと洗っちゃうね」と声をかけておくことで、子どもも安心して待ってくれますよ。
安全と楽しさを両立させる工夫が、ワンオペ育児の強い味方になります。
工夫③:お風呂あがりの動線を整える

お風呂そのものも大変ですが、実は「お風呂あがり」がもっとバタバタするという声も多くあります。
とくに寒い季節や、兄弟がいる場合は、体を冷やさないようにしながら全員のケアを手早く済ませる必要があります。
脱衣所やリビングに、タオル・着替え・おむつ・保湿クリームなどをひとまとめにしてセットしておくと、お風呂上がりの流れが格段にスムーズになりますよ。
たとえばリビングの隅に「お風呂上がりステーション」を作っておくと、すぐに着替えさせたり保湿ケアができて便利です。
動線が整っていれば、赤ちゃんが泣いても焦らず対応でき、上の子のお世話との同時進行もしやすくなりますよ。
何もないところから1から用意するのではなく、セット化しておくことが、ワンオペ育児においてはとても大きな時短になります。
工夫④:一人で抱え込まない仕組みづくり

ワンオペ育児で最も陥りやすいのが、「自分だけで何とかしなきゃ」という気持ちです。
確かに現実的に頼れる人がいない状況もありますが、「ちょっとだけ助けてもらう」ことができる仕組みを用意しておくことも、ひとつの大事な工夫です。
たとえば、パートナーに「週末だけでも子どもと一緒に入ってもらう日」を決めたり、祖父母に短時間だけ来てもらう工夫もありますよ。
さらに、自治体のファミリーサポートや一時保育、ベビーシッターサービスを利用することも検討してみてください。
「手を抜くこと=悪いこと」ではありません。むしろ、ワンオペを続けて心身がボロボロになる前に、誰かに頼る選択肢を持つことが、育児を長く続けるためにとても大切な視点なのです。
工夫⑤:ママ自身の「心の余裕」を作るコツ

ワンオペで毎日必死にがんばっていると、「自分の時間なんてとれない」「ゆっくりする暇もない」と思いがちではないでしょうか。
でも、育児には「余白」が必要です。少しでも心の余裕を取り戻す工夫をすることで、気持ちの持ちようが大きく変わりますよ。
子どもが寝たあとに10分だけ好きなことをする、自分へのごほうびにスキンケアタイムを楽しむなど、たとえ短時間でも「自分を大切にする時間」を意識的に取ってみてください。
誰かに頼ることが難しい日でも、自分の中で「ここだけは譲らない」というリズムを作ることで、日々の気持ちが穏やかになります。
心の余裕は、育児のしんどさを軽くする第一歩でもあるのです。
ワンオペ育児の限界を感じたときの対処法

どれだけ工夫を重ねても疲れが抜けず、怒りっぽくなったり涙が止まらなかったりする時期がないでしょうか。
ワンオペの渦中にいると自分の限界を客観視しにくく、つい「まだ頑張れる」と踏ん張ってしまいがちです。
しかし心身が崩れてしまってから立て直す方がずっと大変ですよね。
育児は本来チーム戦であり、助けを求める行動そのものが前向きな工夫であると捉え直すことが、長期戦を乗り切る第一歩になります。
慢性的な寝不足で朝起き上がれない、食欲が極端に乱れる、子どもに強く当たってしまい自己嫌悪が続く、涙が出やすく夜になると気持ちが沈んだりする等、こうした変化は心の疲労シグナルです。
ワンオペ育児では小さなストレスが雪だるま式に膨らみやすいため、軽いうちに休む日をつくる、家事タスクを減らす、信頼できる相手に話すなど緊急避難的な工夫を差し込みましょう。
自治体が用意するサポートは下記の様なものがあります。
〇 一時預かり
〇 ファミリーサポート
〇 子育て支援センターの短時間利用
〇 産後ケア事業
〇 訪問型ヘルパー
利用料に助成が出る地域もあるので、市区町村の子育て窓口に「ワンオペでお風呂が大変」「夜の育児負担を軽くしたい」と率直に相談してみてください。
制度の仕組みや申し込み手順を教えてもらえるだけでなく、組み合わせ方の提案を受けられることもあります。
利用者の声が集まるほど支援が拡充される例もあるため、助けを求める行動自体が地域全体の育児環境を良くする工夫につながります。
まとめ|ワンオペ育児は「がんばりすぎない工夫」でラクになる

ワンオペ育児は、一人で頑張ることが美徳ではありません。家族や友人、自治体の支援や一時保育など、利用できるサポートは遠慮せずに活用してください。
お風呂や食事といった毎日の小さなことでも、すべてを一人で担うのは本当に大変です。
だからこそ、「無理なく続けられる工夫」や「ちょっとしたコツ」を取り入れて、少しでもラクになることが大切ですよ。
あなたの負担が軽くなれば、それは子どもにとっても大きな幸せにつながります。そして何より大切なのは、「自分を責めないこと」です。
頑張っていること自体がすでにすばらしいことです。「私は今、よくやっている」と自分に言ってあげてくださいね。
疲れたとき、迷ったときには、またこの記事に戻ってきてくださいね。あなたは一人じゃありません。応援しています!